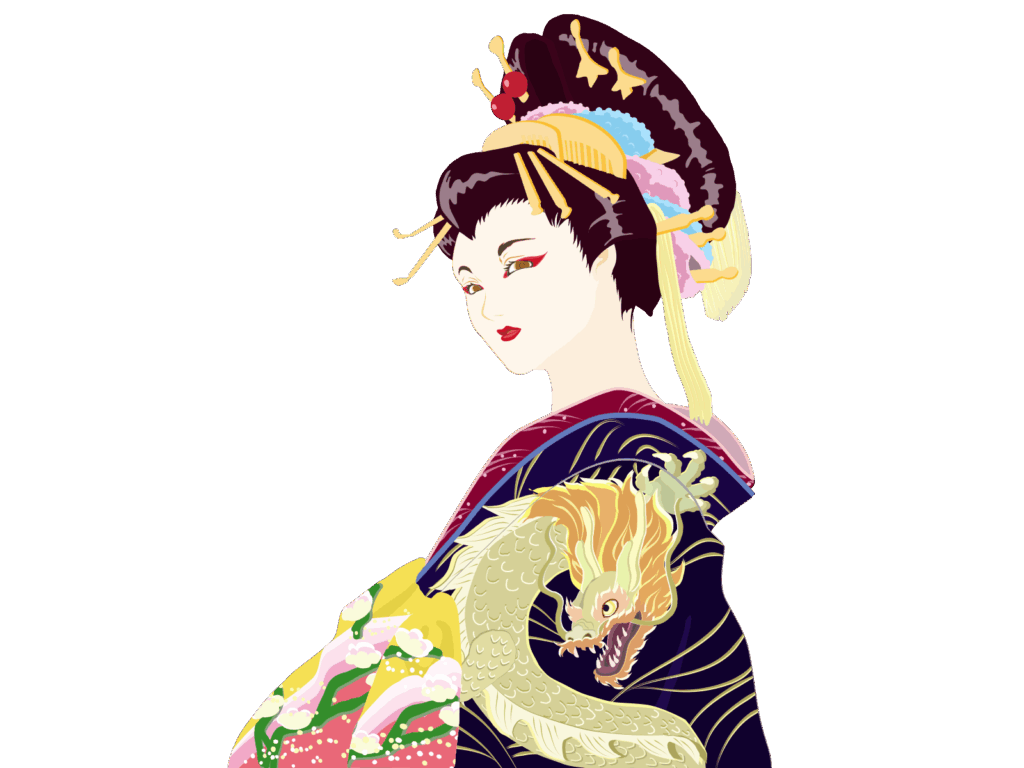花魁が出てくるドラマ べらぼう第十二話をまとめてみました
2025年10月31日

美しい花魁写真なら、スタジオ八色へ
「特別な一枚を残したい」「華やかな花魁姿を体験してみたい」——そんな想いをお持ちの方は、ぜひスタジオ八色へお越しください。
千葉県千葉市にある花魁写真スタジオ八色では、丁寧なお支度と本格的な撮影で、あなたの魅力を最大限に引き出します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、経験豊富なスタッフが心を込めてサポートいたします。
撮影の雰囲気や仕上がりは、公式Instagramでもご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
スタジオは、最寄り駅から徒歩1分とアクセスも良好。近隣にコインパーキングもございますので、お車でも安心してお越しいただけます。
ご質問・ご予約はLINEやメールでも受け付けております。お気軽にご相談くださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
こちらのページではドラマ べらぼう第12話について情報をまとめてみました。
スタジオ八色は花魁写真撮影スタジオをやっております。
是非皆様、撮影にお越しいただければ幸いです。
右下のLINEからお気軽にお問い合わせください。
べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第12話あらすじ
序章:再び動き出す吉原の祭り
江戸・吉原。華やかでありながら、どこか倦怠を帯びた遊里の空気が漂うなか、前回の祭りの失敗を反省した親父たちが「今年こそは」と再起を期す。彼らの狙いは、商売の立て直しだけでなく、沈みかけた吉原全体の勢いを取り戻すことにあった。中心に呼び出されたのは、若き出版人・蔦屋重三郎。蔦重は“見る者を惹きつけ、残るもの”を作る才覚を買われ、今年の祭りの企画を託されることになる。
蔦重は、ただの遊びや宴ではなく、「記録と表現」を結びつけた祭りを構想する。彼にとって、吉原は一時の快楽を売る場所ではなく、ひとつの文化の坩堝であり、そこに生きる人々の息づかいを描き残すべき舞台だった。こうして、のちに“俄祭り”と呼ばれる一大イベントの準備が始まる。
第一章:若木屋の宣言と派閥の火種
廻状がもたらす衝撃
そんな中、若木屋が突如として廻状を回す。「八月の一ヶ月、俄祭りを催す」という宣言と共に、祭りに合わせて錦絵『青楼俄狂言尽』を出版するという内容だった。吉原の他の見世は驚きと憤りを隠せない。商売敵の大文字屋の親父は「出し抜かれた」と怒号を上げ、遊里は一夜にして二つの陣営に分かれることになる。
しかし蔦重は、この対立をむしろ好機と見た。競い合うことで吉原全体が動き出す。その構図こそ、彼が求めていた「見せ物としての盛り上がり」だったのだ。彼は各店に働きかけ、祭りの企画を“見世全体を巻き込む文化催事”へと押し上げていく。
駆け引きの始まり
若木屋は芸妓や遊女を総動員し、艶やかで大胆な演目を準備。一方の大文字屋は、格式を重んじた上品な芝居で対抗する。どちらが客の心を掴むか、駆け引きは激しさを増す。蔦重はその動きを冷静に観察しながら、「この一連の熱狂を、後世に残せる形にする」という構想を密かに練り始めていた。
第二章:平沢常富という男
謎めいた協力者
蔦重が出版記録の構想を練るなか、ひとりの男が現れる。平沢常富。表向きは旗本の書役だが、その正体は戯作者・朋誠堂喜三二である。彼は世の中の機微をよく知り、文筆の才にも長けた人物だった。蔦重は、彼の中に“言葉で時代を残せる者”としての魅力を見出す。
当初、蔦重は平賀源内に祭りの仕掛けを書かせようとするが、源内は発明の仕事に没頭しており、関与を断る。代わりに平沢が裏方として祭りの記録、そして出版企画に関わることになる。彼は祭りの本質を「瞬間の輝き」と捉え、蔦重の“記録”という志と共鳴していく。
筆が生み出す新たな火種
平沢は祭りを題材にした戯作『明月余情』の草稿を執筆し始める。その文体は軽妙でありながらも、どこか皮肉と哀しみを帯びていた。彼の筆は、祭りを単なる娯楽としてではなく、“生と死、表と裏が交錯する現実”として描き出していく。蔦重は彼の才能を確信し、この原稿を錦絵とともに出版することを決意する。
第三章:俄祭り、開幕
華やかさと喧騒の幕開け
八月。ついに俄祭りが開幕する。見世ごとに趣向を凝らした出し物が連日行われ、吉原中が色と音に包まれる。道には提灯が並び、芸妓の唄、客の笑い声、商人たちの呼び込みが入り混じる。普段は閉ざされた遊里が、ひとときだけ“開かれた町”へと変貌する瞬間だった。
俄の演目は即興性が命。若木屋は艶やかで笑いを誘う芝居を展開し、大文字屋は品格を重視した古典調で魅せる。互いの客引き合戦は熾烈を極め、吉原は一夜ごとに熱を帯びていく。蔦重はその光景を記録しながら、心の中で「これこそが江戸の生きた芸だ」と呟く。
裏側に潜む思惑
一方、祭りの裏では策略が渦巻く。若木屋の番頭が他店の客を引き抜こうとし、大文字屋が密かに役者を買収する。表では華やかに笑い合い、裏では陰湿な駆け引きが繰り広げられる。蔦重はそのすべてを“人間の業の縮図”として見つめ、記録する価値を感じる。
第四章:うつせみと新之助の決断
遊里の片隅の恋
祭りの喧騒の中で、ひとつの静かな物語が芽生える。若木屋に仕える女郎・うつせみと、帳場に立つ小田新之助。互いに惹かれながらも、身分と境遇の壁が二人を隔てていた。祭りの夜、人々の笑い声と太鼓の音が響くなか、うつせみは新之助に言う。「外の月、見たことある?」と。
二人は人混みを抜け、吉原大門へ向かう。そこは遊女が決して越えてはならない境界。だがこの夜、彼らは一歩を踏み出す。静かに門を出るシーンは、祭りの喧噪と対照的に、深い余韻を残す象徴的な瞬間となる。
第五章:明月余情 — 記録としての文化
出版の決意
祭りの最終日、蔦重は平沢に言う。「この熱を、形に残そう。」その言葉が『明月余情』の誕生を決定づけた。平沢の文章と蔦重の編集、絵師たちの錦絵が合わさり、俄祭りの熱狂を記録した一冊が生まれようとしていた。彼らが目指したのは、単なる売り物ではなく“時代の証言”である。
終わりと始まり
俄祭りが幕を閉じる頃、吉原には再び静けさが戻る。しかし、その静けさの底には確かな変化があった。蔦重は新たな出版の道を見つけ、平沢は戯作者として名を広める兆しを見せる。うつせみと新之助の姿は消えたが、彼らの選択は吉原という檻の外に“自由”という新たな物語を刻んだ。
終章:江戸の夢と余情
第12話のタイトル「俄なる『明月余情』」は、まさにこの回を象徴している。俄=即興の芸が放つ刹那の光、そして明月=変わらぬ月が照らす情の余韻。その対比の中に、蔦重が生きた時代の美意識が宿る。華やかで、哀しく、しかし確かに“生きた”江戸の人々の姿がそこにある。
物語のラストで蔦重が見上げた月は、彼が追い求める「記録の光」を象徴していた。芸と商い、欲と情、記録と忘却——そのすべてを抱えながら、江戸という都市の文化は息づいていく。祭りの喧騒が遠ざかる中、彼の心にはひとつの言葉が残る。「べらぼうに面白ぇ」。そして物語は静かに幕を閉じる。

美しい花魁写真なら、スタジオ八色へ
「特別な一枚を残したい」「華やかな花魁姿を体験してみたい」——そんな想いをお持ちの方は、ぜひスタジオ八色へお越しください。
千葉県千葉市にある花魁写真スタジオ八色では、丁寧なお支度と本格的な撮影で、あなたの魅力を最大限に引き出します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、経験豊富なスタッフが心を込めてサポートいたします。
撮影の雰囲気や仕上がりは、公式Instagramでもご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
スタジオは、最寄り駅から徒歩1分とアクセスも良好。近隣にコインパーキングもございますので、お車でも安心してお越しいただけます。
ご質問・ご予約はLINEやメールでも受け付けております。お気軽にご相談くださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。